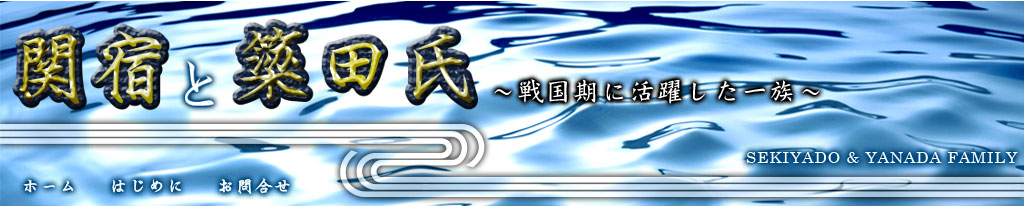はじめに
関宿は、関東平野のほぼ中央に位置し、最北端は利根川と江戸川の分流点となっています。現在、この場所には、城を模した千葉県立関宿城博物館が建っています。
江戸時代、関宿は伊達氏など奥州の外様大名への備えとして、久世氏、牧野氏、板倉氏などの譜代大名が代々配置されてきました。
また、江戸湾に流れていた利根川の流れを東に瀬替えした利根川の東遷事業が行われ、治水対策と共に水上交通網の整備や新田開発などが進められ、利根川と江戸川がつながることで、銚子と江戸が内陸水路による舟運で結ばれ、奥羽地方からの物資の運搬に危険な外海の房総沖を通らずに済むことになったことから、関宿はその中継基地としても大きく栄えました。
このように江戸時代、関宿は重要な地であったことは、有名なことですが、江戸時代前の戦国時代にも、関宿は軍事的な戦略拠点として、また多くの川が入り込んだ内陸交通路の要衝として、重要な土地と見られていました。
この戦国時代の関宿で活躍したのが、簗田一族でした。簗田氏は、古河公方の重臣として、古河城の前衛基地である関宿城に置かれ、前半は敵対していた関東管領の上杉氏への備えとして、上杉氏の没落後の後半は小田原北条氏の北関東侵攻への備えとなりました。
このホームページは、戦国時代の関宿を舞台として活躍した簗田氏の盛衰について紹介します。関宿を中心としたこのエリアに興味をお持ちいただければなによりです。
そのほか、野田市関宿、境町、五霞町に在る名所・旧跡や史跡の紹介、各地の特産品や食事処などの情報も掲載します。ご来訪の機会にご利用いただければと思います。
なお、このホームページは、国の地方創生加速化交付金を受けて、千葉県野田市、茨城県境町、同じく五霞町の1市2町が、広域連携による利根川・江戸川の魅力を活用した観光地域づくりの一環として開設したものです。 (野田市自然経済推進部商工観光課)