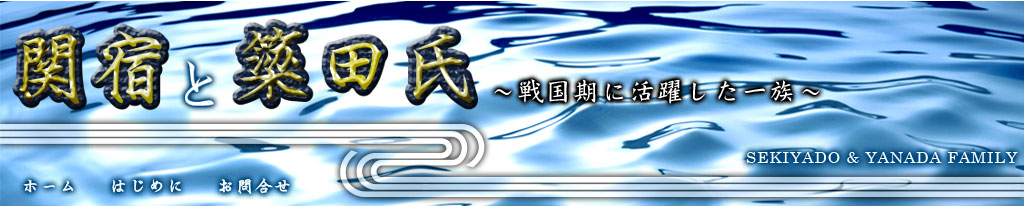野田市(関宿地区)の名所旧跡
船橋随庵先生水土功績の碑

船橋随庵(ふなばしずいあん)は、1795年(寛政7)に関宿藩士・船橋周能の次男として関宿に生まれます。1848年(嘉永元)には関宿藩中老となり、その年の10月から、関宿江戸町から莚打までの約20キロメートルに及ぶ「関宿落堀」の治水工事を始めます。その基礎は、若いころに治水工事を伊奈家の関東流と井沢為永の紀州流から学んだもので、1850年(嘉永3)に工事は完成しました。本来、関宿落堀は洪水などで関宿城内に溜まった水を城外へ逃がすための排水路だったようですが、随庵の治水工事により、水害から村々を守るとともに、利用できなかった土地を米や作物が生産できるようにする一方で、農民に対して新しい土地の配分も行いました。
また、随庵はペリーが来航して以来、開国論や攘夷論が高まる中で、各地で起こった農兵論を提唱した一人でした。明治政府は、随庵の才能を惜しみ、新政府に参画させようとしましたが、老齢のため固辞したといい、1872年(明治5)78歳で亡くなりました。碑は、1895年(明治28)年に建立されたものです。(写真は「関宿落堀」)
(野田市関宿台町)